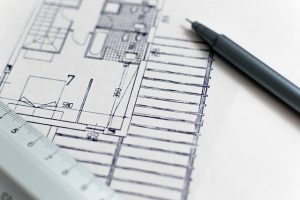042-318-0450
受付9:00~18:00 日曜祝日定休
【事業承継税制を使えば贈与税 0 円?】本当に節税対策はいらないのかを徹底解説!
◆ はじめに:「贈与税 0 円」の誘惑
「事業承継税制を使えば贈与税は 0 円になりますよ」
こんなセールストークを保険営業や税理士から聞いたことがある経営者の方も多いのではないでしょうか?
たしかに、事業承継税制を使えば、贈与税や相続税を“実質ゼロ”にすることが可能です。ところが、それは あくまで「条件付きの猶予」 にすぎません。下手をすれば、将来、莫大な税金をまとめて払う羽目になるリスクもあるのです。
この記事では、「贈与税 0 円になるから節税対策はいらないのか?」という疑問について、制度のしくみとリスク、そして実務的な視点からわかりやすく解説していきます。
◆ そもそも事業承継税制とは?
事業承継税制とは、中小企業の経営者が自社株を後継者に贈与や相続で渡すときに発生する贈与税・相続税を“猶予”してくれる制度です。一定の条件を満たせば、最終的には 免除(ゼロ) されます。
【制度の対象となるもの】
- 非上場の自社株式(会社の持ち株)
- 贈与税・相続税が対象
- 適用には「都道府県知事の認定」が必要
◆ 実は「税金ゼロ」ではない!そのカラクリとは?
「贈与税がかからない」と聞くと、“もう払わなくていい”と誤解しがちですが、それは間違いです。
正確には「猶予」であって「免除」ではない!
税金は一旦「猶予」されますが、要件を満たし続けることが前提です。万が一、条件から外れると、猶予されていた税金が全額ドンッと課税されてしまいます。
◆ 猶予が打ち切られるとどうなるの?
以下のような事態になると、猶予は終了し、贈与税や相続税が即時に課税されます。
| ケース | 結果 |
|---|---|
| 後継者が5年以内に代表取締役を辞任 | 猶予打ち切り、贈与税が課税 |
| 株式を売却・譲渡した | 同上 |
| 会社が解散・廃業した | 同上 |
| 定期的な報告義務を怠った | 同上 |
| 株式を担保に入れた | 同上 |
つまり、「猶予=永久に払わなくていい」ではなく、「ちゃんと経営し続けていれば課税しないでおいてあげるよ」というだけなのです。
◆ なぜ節税対策は今でも必要なのか?
① 制度の適用対象にならない企業もある
事業承継税制を使えるのは、あくまで中小企業のうち、一定の要件を満たす法人のみ。たとえば…
- 業種が対象外
- 資本金や売上が要件をオーバー
- 株主構成が複雑で適用できない
などの場合、そもそも制度を使えません。
② 制度を使っても“全体の相続税”は減らないことがある
たとえば、長男が後継者として株をもらい、税金が猶予されても、他の兄弟が現金や不動産を相続して相続税がかかる場合、相続税対策は別途必要になります。
③ 会社の将来に柔軟性がなくなる
事業承継税制を使っている間は、株式の売却や事業売却、M&A が原則できません。
事業がうまくいかずに会社を売却しようと思っても、猶予が打ち切られ、莫大な税金が一気に発生する可能性があります。
④ 制度改正リスクがある
今は特例で 100%猶予されますが、将来この制度が廃止・縮小される可能性もあります。そうなれば、途中で税金を払わなければならなくなるリスクも。
◆ 節税と事業承継税制の「併用」が正解
節税対策は「しないでいい」のではなく、「事業承継税制と上手に併用すべき」なのです。
たとえば…
- 自社株評価の引下げ(配当を抑える、利益を出しすぎないなど)
- 株式の一部を持株会社に移転して管理
- 相続対策として保険を活用
- 不動産を活用した資産分散
- 他の相続人に代償分割資金を準備する
など、税額そのものを圧縮する努力は不可欠です。
◆ 実際の現場ではどう対応している?
多くの中小企業では次のようなステップで進めています:
- 事業承継税制の対象になるかどうか確認
- 自社株の評価額をシミュレーション
- 贈与か相続か、承継方法を検討
- 他の相続人との公平性を考慮(代償分割など)
- 制度の適用申請(認定手続き)と税理士・行政書士との連携
- 同時に株価引下げや資産防衛策を講じる
◆ まとめ:制度を「過信せず、活かす」
| 誤解 | 実際 |
|---|---|
| 事業承継税制を使えば贈与税はゼロ | 条件付きで「猶予」、打ち切りリスクあり |
| 税金対策はもういらない | むしろ併用しないとリスクが高まる |
| 誰でも使える制度 | 一部の中小企業しか対象にならない |
| 株式を持っていれば安心 | 売却やM&A時に重課税されることも |
◆ 最後に:専門家と一緒に“設計”するのが鍵
事業承継税制は、中小企業にとって非常に強力な制度です。ただし、その正しい理解と活用方法がなければ、逆に大きなリスクを抱えることにもなります。
節税対策を「やめる」のではなく、「制度と併用して最適化する」ことが成功へのカギです。
自社の状況にあわせたオーダーメイドの事業承継プランを、税理士や行政書士などの専門家と一緒に考えることをおすすめします。