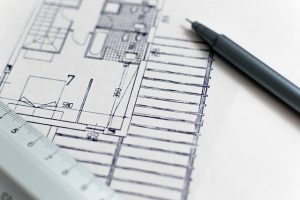042-318-0450
受付9:00~18:00 日曜祝日定休
【2025 年最新】特定技能 1 号・2 号の違いと建設業界のリアルな実態!外国人労働者が現場を支える時代へ
日本の建設現場では、今や外国人労働者の存在が欠かせないものとなっています。特に「特定技能 1 号」や「特定技能 2 号」といった在留資格を持つ外国人が、実質的に“現場の屋台骨”となっているといっても過言ではありません。
しかし、こうした外国人労働者の制度や実態について、誤解も多く存在しています。なかでも、「特定技能実習生」という耳慣れた言葉が使われる場面では、制度の混同が起きがちです。本記事では、特定技能 1 号と 2 号の違いをわかりやすく解説し、建設業における外国人労働者のリアルな実情や今後の課題について、行政書士や建設業関係者向けに深掘りしていきます。
◆「特定技能実習生」という言葉に要注意!
まずは言葉の整理から。
「特定技能実習生」というのは、実は正式な制度名ではありません。現場では以下の 2 つの在留資格が混同されて、まとめてこう呼ばれることがあります。
- 技能実習生(技能実習制度):技術を学び、母国に持ち帰るための制度(建前)。
- 特定技能外国人(特定技能制度):日本の人手不足を補うための制度(実質的に労働力)。
建設現場ではこの両者が並行して働いており、制度を正しく理解していないと、労務管理や支援体制に大きな齟齬が出る可能性があります。
◆特定技能 1 号と 2 号の違いを徹底解説
では、本題である「特定技能 1 号」と「2 号」の違いを見ていきましょう。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留目的 | 即戦力として働く | 熟練技能者として定着 |
| 在留期間 | 最長5年(更新制) | 無期限(永住可能) |
| 家族の帯同 | × 不可 | 〇 配偶者・子ども可 |
| 対象職種 | 建設・外食・介護など12分野 | 現在は建設業・造船など限定的 |
| 必要試験 | 技能試験・日本語試験 | より高度な技能試験 |
| 支援体制 | 登録支援機関が義務 | 自立が前提 |
特定技能 1 号は、いわば「入口的ポジション」であり、特定技能 2 号は「熟練工」としての高ステータスです。特定技能 2 号に移行すれば、在留期限の上限がなくなり、家族の帯同も認められるという大きなメリットがあります。
◆建設業での実態:外国人労働者がいないと現場が止まる?
建設業界では、少子高齢化や若手の業界離れにより、深刻な人手不足が続いています。そのため、技能実習生や特定技能外国人は、鉄筋工、型枠大工、配管、内装仕上げなどの現場で不可欠な存在となっています。
特に近年は、「技能実習 2 号修了者」が試験免除で特定技能 1 号へ移行できるため、同じ職場でそのまま継続就労するケースが増加中です。
メリット
- 安定した労働力の確保
- 真面目で勤勉な人材が多い
- 技術の定着が進んでいる
課題も山積み
- 言語の壁:日本語能力が不十分なまま現場に出され、安全リスクになるケースも。
- 人権問題:低賃金、長時間労働、寮環境などに問題を抱える現場も。
- キャリアの不透明さ:特定技能 2 号への道筋が見えにくく、本人・企業双方にとって将来設計が立てづらい。
◆特定技能 2 号は“建設業の救世主”になるか?
特定技能 2 号に移行すれば、在留期限の制限がなくなり、家族も呼べるようになります。これは「一時的な労働力」から「日本に定着する人材」へのシフトを意味します。
とはいえ、現在(2025 年)は建設業と造船分野にしか特定技能 2 号が認められておらず、試験も非常に難易度が高いため、移行者数はまだ少ないのが現状です。
しかし将来的には、他分野への拡大や試験制度の見直しによって、特定技能 2 号を中心とした受け入れ体制が本格化すると見られています。
◆技能実習制度は廃止へ、新制度「育成就労」へ移行予定
2027 年を目処に、技能実習制度は廃止され、より実態に即した「育成就労制度(仮称)」へ一本化される見込みです。
この制度では、人材育成だけでなく、職場定着やキャリア形成を視野に入れた制度設計がなされる予定であり、建設業界もその対象となるでしょう。
◆まとめ:特定技能人材は“パートナー”へ
建設業における外国人労働者は、単なる「助っ人」ではなく、今後は「日本で暮らす仲間」「職場の一員」として共に働いていく存在です。制度への理解と適切な対応が、日本人と外国人の双方にとってより良い未来をつくる鍵となります。
この記事が参考になった方は、建設業の人手不足対策や外国人雇用に関する最新情報を継続チェックしてみてください。制度は変化し続けています。今こそ、制度理解と戦略的対応が求められる時代です。