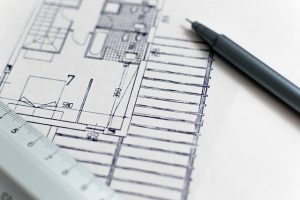042-318-0450
受付9:00~18:00 日曜祝日定休
建設業許可が必要となる請負金額の基準について
建設業を営むにあたり、「許可が必要な工事」と「許可が不要な工事」の基準について正しく理解しておくことは非常に重要です。特に、複数の業種にまたがる工事を請け負う場合、金額の基準を超えると建設業許可が必要となるケースがあるため注意が必要です。本記事では、建設業許可の要件や500万円基準の適用方法について、わかりやすく解説します。
建設業許可が必要な場合とは?
建設業法では、特定の金額を超える工事を請け負う場合には、都道府県知事または国土交通大臣の建設業許可が必要となります。
許可が必要な基準
1. 建築一式工事の場合
• 1件の請負金額が1,500万円以上(税込)
• 木造住宅で延べ面積が150㎡以上
2. 専門工事(建築一式工事以外)の場合
• 1件の請負金額が500万円以上(税込)
この基準に該当しない小規模な工事であれば、建設業許可を取得していなくても施工することが可能です。しかし、請負金額が上記の金額を超える場合は、許可がないと工事を請け負うことができません。
複数の業種を組み合わせた工事の取り扱い
「一つの業種ごとに500万円以下であれば、許可は不要」と考える方もいますが、工事全体の合計金額が500万円以上になる場合は、許可が必要となります。これは、建設業法において「1件の工事」として取り扱われるためです。
例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。
許可が不要なケース
• 電気工事:400万円
• 内装仕上工事:80万円
• 合計:480万円(許可不要)
この場合、請負金額の合計が500万円未満のため、許可は不要です。
許可が必要なケース
• 電気工事:400万円
• 内装仕上工事:150万円
• 合計:550万円(許可が必要)
このように、各工事の単価が500万円以下であっても、工事全体の請負額が500万円以上になる場合は許可が必要となる点に注意しましょう。
「分割発注」による許可逃れはNG
許可の取得を避けるために、発注者が工事を複数に分割して契約するケースがありますが、これも違法となる可能性があります。
建設業法では、工事の内容や場所、発注者が同一の場合、形式上分割されていても実質的に「1件の工事」とみなされることがあります。つまり、
• 工事の目的が共通している
• 同じ現場で連続して施工される
• 契約を細かく分けているが、全体としての工事が一体とみなされる
といった場合、許可が必要になる可能性が高くなります。
許可を取得しないで工事を行った場合のリスク
建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、以下のようなリスクがあります。
1. 行政処分や罰則
• 無許可営業として、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
2. 取引先の信頼失墜
• 許可が必要な工事を無許可で行ったことが発覚すると、元請業者や施主からの信頼を失う恐れがあります。
3. 工事契約の無効化
• 契約自体が法的に無効とされる可能性があり、工事代金を回収できない事態にもなりかねません。
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得することには、単に法律を遵守するだけでなく、以下のようなメリットがあります。
1. 信頼性の向上
• 許可を持つことで、元請業者や施主からの信頼を得やすくなります。
2. 受注機会の拡大
• 許可があることで、より大規模な案件や公共工事への参加が可能になります。
3. 経営の安定化
• 許可業者としての社会的信用が高まり、金融機関からの融資が受けやすくなるといった利点もあります。
まとめ
建設業許可が必要かどうかの判断は、請負金額や工事内容を正確に把握することが重要です。
• 専門工事の請負金額が500万円以上の場合は許可が必要
• 複数の業種を組み合わせた工事は、合計金額が基準を超えると許可が必要
• 許可逃れのための分割発注は違法とされる可能性がある
建設業を営む上で、法令遵守は事業の継続に不可欠です。許可が必要な場面を正しく理解し、適切に対応することが大切です。