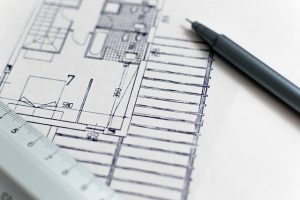042-318-0450
受付9:00~18:00 日曜祝日定休
建設業許可における事業承継と相続の違いとは?多摩地域(調布・府中・稲城市)を中心に徹底解説!
建設業を営む上で欠かせない「建設業許可」。しかし、経営者の代替わりや万一の相続が発生した場合、この許可はどうなるのでしょうか?実務では「事業承継」「相続」「承継認可申請」など、似ているけれど異なる制度が存在し、混乱しやすい分野です。特に多摩地域(調布市・府中市・稲城市など)で地元密着の建設業を営む方にとっては、経営の継続や取引先との信頼関係に直結するため、正しい理解が不可欠です。
この記事では、専門的な建設業許可制度を、わかりやすく・面白く、そして地域に根差した観点から解説していきます。
1. 建設業許可は「財産」ではなく「営業資格」
まず押さえておきたい大前提は、建設業許可は財産ではないという点です。不動産や預貯金と違い、相続の対象にはなりません。許可は「法人」または「個人事業主」という主体に付与されている“営業資格”です。そのため、誰かが亡くなったときに自動的に子どもに相続されるものではありません。
ここを誤解すると、いざ承継の場面で「え? 許可って相続できないの?」という大問題が起こります。実務ではこれが原因で工事契約に支障が出るケースも見られます。
2. 事業承継と建設業許可
法人の場合
- 会社自体が存続している限り、建設業許可は消滅しません。
- 代表取締役が父から子へ交代した場合でも、法人格は同じなので許可は維持されます。
- 必要なのは「変更届」の提出のみ。特に重要なのは、
- 代表取締役の変更
- 経営業務管理責任者(経管)の交代
- 専任技術者の交代
- これらの変更は、知事許可なら2週間以内、大臣許可なら30日以内に変更届を提出する必要があります。
個人事業の場合
- 個人の許可は「その人固有のもの」であり、子や配偶者に引き継ぐことはできません。
- 後継者が建設業を続けたい場合は、新規許可申請が必須です。
- 営業に空白期間が生じないよう、廃業届と新規許可申請を計画的に行う必要があります。
つまり、「法人」なら変更届で済むが、「個人」は新規許可を取る必要がある、という違いがあります。
3. 相続と建設業許可
法人の場合
法人は代表者が亡くなっても会社自体は存続します。したがって、建設業許可も失効しません。ただし代表取締役変更の登記を行い、速やかに変更届を出す必要があります。
個人の場合
個人事業主が亡くなると、許可は即時に失効します。ここが非常に重要なポイントです。営業を続けたくても「無許可営業」となってしまう危険性があります。
ただし、建設業法には特例が設けられています。被許可者が死亡した場合、相続人が30日以内に承継届を提出すれば、最長3年間は亡くなった方の許可を使って営業を継続できるという制度です。この間に相続人が新規許可を取得する準備を進めます。
つまり、相続の場合は「死亡から30日以内」という極めてタイトな期限があるのです。
4. 合併・会社分割・事業譲渡と承継認可申請
ここで登場するのが「承継認可制度」です。法人が合併や会社分割、事業譲渡などを行う場合、法人格が変わるため許可は原則失効します。しかし、それでは取引先や公共工事に大きな混乱が生じます。そこで設けられているのが、承継認可制度です。
- 承継認可を受ければ、新法人が旧法人の許可を引き継げます。
- 申請期限は承継の効力発生日の前日まで。これを過ぎると新規許可申請しか方法がなくなります。
- 特に公共工事を多く受注している会社では、承継認可を怠ると入札参加資格に大きな穴が開いてしまうため、致命的です。
法人の再編(合併・分割・譲渡)では「承継認可申請」が必要であることを絶対に忘れてはいけません。
5. 事業承継・相続・承継認可の違いまとめ
| 区分 | 法人 | 個人 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 事業承継 | 変更届でOK | 新規許可申請が必要 | 法人は許可存続、個人は不可 |
| 相続 | 許可存続(法人) | 即失効、30日以内に承継届 | 個人は特例で最大3年猶予 |
| 合併・分割・譲渡 | 承継認可申請が必要 | - | 発生日前日までに申請必須 |
6. 多摩地域(調布・府中・稲城市)の実務上の注意点
- 調布市:公共工事の入札参加資格を持つ会社が多く、承継認可を忘れると入札停止のリスク大。
- 府中市:老舗の建設業者が代替わりするケースが多く、代表交代時の変更届忘れが散見される。
- 稲城市:個人事業で営んでいる業者が多く、経営者の高齢化による相続問題が顕在化。30日以内の承継届を失念して無許可扱いになる事例も懸念される。
地域密着の建設業者ほど「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにしがちですが、建設業許可に関しては期限管理が命綱です。
7. 面白く理解するための例え話
- 法人承継は「家族が代わっても店の看板はそのまま」状態。お客さんから見ても違和感なし。
- 個人の相続は「店主が亡くなったら店の営業許可証が失効」するイメージ。息子が同じ料理を作れても、新しい営業許可証を取らないと店は開けない。
- 承継認可制度は「店を別の会社に売るときに、営業許可も一緒に引き継げる仕組み」。ただし“売却日の前日まで”に役所へ申請が必要。
8. まとめ:建設業許可を守ることは事業を守ること
建設業許可は、事業そのものを支える「営業のライセンス」です。これを切らしてしまうと、工事契約が履行できなかったり、公共工事の入札資格を失ったりと、事業の存続に直結します。
- 法人承継なら変更届を忘れずに。
- 個人の相続なら30日以内に承継届を提出し、新規許可準備を怠らない。
- 合併・分割・譲渡なら承継認可を効力発生日前日までに申請。
特に調布市・府中市・稲城市といった多摩地域で建設業を営む方々にとって、これは決して他人事ではありません。早めに行政書士など専門家へ相談し、備えておくことが安心への第一歩です。
結論:建設業許可は“財産”ではなく“資格”。承継の形によって手続が大きく変わるので、期限管理と専門家の活用が成功の鍵です。