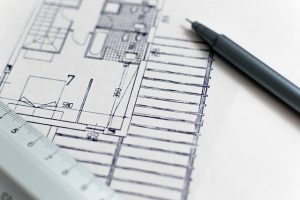042-318-0450
受付9:00~18:00 日曜祝日定休
【完全解説】特定建設業・一般建設業・指定建設業の違いとは?金額基準と許可の必要性もやさしく解説!
建設業界に携わっている方なら一度は聞いたことがある「一般建設業」「特定建設業」、そして「指定建設業」。
似たような名前だけど、何がどう違うのか。誰に、いつ、どんな許可が必要なのか。実は多くの方が誤解しています。
この記事では、建設業許可制度の基本から誤解されやすいポイントまで、実務に役立つ視点でわかりやすく解説していきます。
そもそも「建設業許可」ってなに?
まず大前提として、建設業を営むためには原則として「建設業許可」が必要です。
ただし、1件の請負代金が500万円(税込)未満の軽微な工事のみを請け負う場合は、許可がなくても営業できます(建築一式工事は1,500万円未満 or 延べ面積150㎡未満)。
つまり、
- 「500万円未満ならそもそも許可はいらない」
- 「500万円以上の工事を請け負うなら、一般か特定かの許可が必要」
というのが基本です。
「一般建設業」と「特定建設業」の違いとは?
一般建設業とは
- 比較的小規模な工事を受注・施工する場合の許可です。
- 自社で施工する、または500万円(税込)未満の下請に出すことが前提。
つまり、「元請だけど小さい案件しかやらない」「下請を使っても金額が小さい」のであれば一般建設業の許可でOKです。
特定建設業とは
- 元請として大きな工事を受注する際に必要になります。
- 特に下請に出す金額が大きくなる場合は要注意。
最新の基準では以下の通りです:
| 工事の種類 | 下請契約合計金額(税込) | 必要な許可 |
|---|---|---|
| 建築一式工事 | 8,000万円以上 | 特定建設業許可 |
| その他の工事(電気・土木など) | 5,000万円以上 | 特定建設業許可 |
こんな誤解に注意!
「特定建設業=元請、一般建設業=下請」という理解は半分正解・半分誤解です。
実際には、「元請かどうか」ではなく、“どれだけの金額を下請に出すか”が許可の分かれ目。
つまり、元請でも下請に出さずに自社施工すれば一般建設業で済む場合もあります。
「指定建設業」ってなに?
「特定」と「一般」に加えて出てくるのが「指定建設業」。これは少し毛色が違います。
指定建設業とは?
- 国土交通大臣が指定する11業種
- 構造上・高度な専門性が求められる重要工事(例:電気、管、鋼構造物など)
たとえば橋梁、ダム、プラントなど、安全性・公共性の高い工事が多く含まれます。
どういうときに関係するの?
実は「指定建設業」というのは、許可区分そのものではなく、「経営業務管理責任者」や「専任技術者」の要件が厳しくなる業種です。
つまり、指定建設業の許可を取るには、
- 「経営業務管理責任者」は当該業種に関する5年以上の実務経験
- 「専任技術者」は国土交通省指定の資格等を有していること
といった条件が、他業種より厳しめに課されます。
実務に役立つポイントまとめ
一般建設業許可が必要なケース
- 1件あたり500万円(税込)以上の工事を請け負う場合(下請含む)
- 建築一式工事の場合は1,500万円(税込)以上、または延べ面積150㎡超の新築
特定建設業許可が必要なケース
- 元請として工事を受注し、下請に出す金額が以下を超えるとき:
- 建築一式工事:8,000万円(税込)超
- その他工事:5,000万円(税込)超
指定建設業の影響
- 特定の11業種では、許可取得のための人的要件がより厳しくなる
- 業種によっては「技術者の確保」がハードルになることも
【まとめ】あなたの業種・契約形態で本当に必要な許可は?
建設業の許可制度は、「工事の金額」や「元請・下請の区別」「業種」によって、必要な許可が変わります。
| あなたの状況 | 必要な許可 |
|---|---|
| 軽微な工事(500万円未満)だけ請け負う | 許可不要(ただし任意取得も可) |
| 中規模の工事(500万円以上)を自社施工 | 一般建設業許可 |
| 大規模な工事で下請を多く使う | 特定建設業許可 |
| 高度専門性のある11業種 | 指定建設業に該当し、許可要件が厳しくなる可能性 |
まとめのまとめ
- 特定建設業とは:元請として大規模工事を下請に出す場合に必要な許可
- 一般建設業とは:中小規模の工事、または自社施工で済ませる場合の許可
- 指定建設業とは:一部の業種で人的要件が厳格な分類
- 建築一式工事の基準:8,000万円(税込)
- 一般建設業許可が必要なライン:500万円(税込)
必要な許可を取らずに工事を行うと、行政処分や業務停止につながることも。
「自社の状況に合った許可」を、きちんと理解して取得することが、事業の安定と信頼につながります。